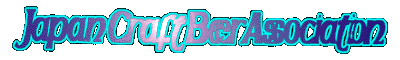 |
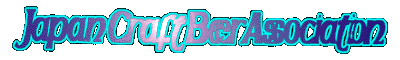 |
| ジャパン・ビアカップ2001 審査講評 |
“ジャパン・ビアカップ 2001” 審査委員長 田村功 |
| 去る4月15日に“ジャパン・ビア・カップ
2001”の審査が行われた。景気の低迷が長引く中でエントリー数の減少が心配されたが、結果として昨年度の実績をかなり上回る67社178銘柄ものビールにご参加いただいた。審査委員長として、心から感謝の意を表したい。 日本地ビール協会が主催するこのビア・コンペティションも、今年で4回目になる。審査を終えた印象は、地ビールの品質が昨年よりも一段と向上しているということである。総じてビア・スタイルの規準に合致しており、完成度においても国際水準を超えているビールが多数見られた。また、ビールの風味や鮮度を損なうオフフレーバーについても問題になるほど濃度の高いものが見られず、その観点からも醸造技術の底辺が着実にレベル・アップしていることを強く感じることができる。 このように全体的に素晴らしい出来映えではあるが、それは審査規準であるビアスタイルガイトラインやオフフレーバー・チェックという“物差し”から見た限りのことであって、必ずしもすべてのビールが忘れがたいほどの魅力を備えているわけではない。ビールは嗜好品であるという原点に立ち返ると、飲む人の「心」に訴えるような強烈な個性や造り手のアピールが欲しいところであるが、そうしたビールは残念ながらあまり多くはなかった。しかし、これについても一昨年、昨年と比べてみれば、着実に増えてきていることは間違いない。この調子で増えると、おそらく来年の“ジャパン・ビア・カップ 2002”では、「個性の光るビール」であるかどうか、「造り手の美学が込められたビール」かどうかが、勝敗の分かれ目となるものと思われる。 次に、印象に強く残ったカテゴリーについて記しておきたい。まずジャーマン・ライトラガー部門であるが、これにはエントリー数がダントツに多かった。全エントリー数の実に16%にも及ぶ。この割合いが現在の地ビールのスタイル占拠率を表すかどうか分からないが、少なくともピルスナー系が地ビールを代表的するスタイルの一つとなったことは間違いあるまい。審査では、一次選考を通過した12銘柄を巡って議論白熱し、3賞を決めるのに難儀を極めた。 ヴァイスビール部門については、例年エントリー数が多く今年も例外ではなかった。しかし、全体の出来映えについては昨年と同レベルあるいは少し落ちたのではないかという印象を持った審査員もいて、品質向上という意味では足踏みしている感がある。とはいえ、日本のヴァイツェン系地ビールは国際的に見ても第一級のレベルを維持していることに変わりはない。入賞したビールは、日本代表として揺るぎのない資格を備えている。 今年のイングリッシュ・ダークエール部門には、高アルコール・ビールのエントリーが格段に増えた。前述した「個性の光るビール」「造り手の美学が込められたビール」へのチャレンジが、この部門に集中したと言える。そういう意味で面白いビールが結構多く見られ、それぞれ飲む人の舌を楽しませてくれる出来映えだが、完成度という観点からはもう一歩の努力が欲しい。今後に大きな期待が寄せられる。 さて、“ジャパン・ビア・カップ 2001”の入賞ビールがすべて試飲できる“ジャパン・ビア・フェステイバル 2001 ”は、ビール・ファンにとってはまたとないチャンスだった。地ビール愛好者はもとより、日頃地ビールに関心の薄い方にも、地ビールのバラエティーの豊かさや品質の高さを改めて認識していただけたものと確信する。 |
HOME |